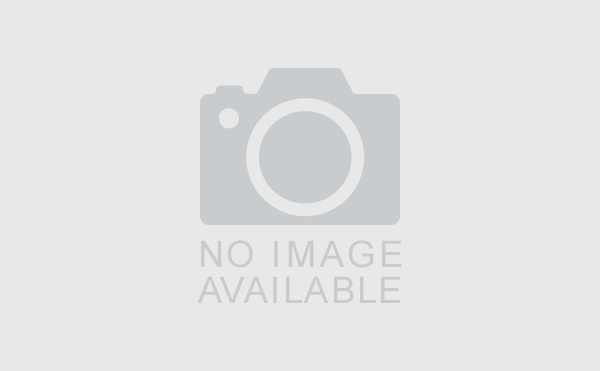映画「どうすればよかったか?」鑑賞
2024年末からミニシアター等で公開されている映画「どうすればよかったか?」を観た。
簡単に説明すると、統合失調症の家族がいる映画監督自身が20年超に渡り家族の苦悩を撮影しまとめあげたドキュメンタリーである。
映画の内容
映画の冒頭は「これは誰が悪いということはない」「統合失調症という病気を解明するものではない」のテキストが現れて、統合失調症のお姉さん(以降、短文にするため敬称略して姉)の叫び音声から始まる。
それぞれが研究者である両親から聡明な頭脳を引き継ぐ姉が生まれ、幼少の写真や映像、監督(以降、弟)が生まれる歴史を軽く説明したあと、1983年の姉24歳時の病気発症、それを取り巻く家族の様相が映し出される。
医大に入った優秀な姉は在学中に精神障害を発症、直後に一度は精神科にかかり、治療を進めるチャンスがあったが、ご両親(特に母)が、「精神病と決めつけるのはマコちゃんに失礼」という言い方をしてそれ以上の診療や投薬を拒み、家に軟禁状態にする。
両親のような研究者を目指していた弟は家族の姿を見て理系の道に進むのは諦め、自暴自棄のようにもなって一般の会社員になったり、興味を持った映像を学んだりして自分の家族をドキュメンタリーとしてまとめることにしたそうだ。
度々自宅に帰っては、不審がられないよう撮影の練習だ、インタビューの練習だなどと方便をつかいその都度映像を撮っていく。
年月が経過するうち姉の発作が激しい怒号になっていったり、言葉が意味を失くして会話が成立しなくなっていく。
そして母も娘に対し興奮して大声を出したりしてこじれていく。
症状が悪化していくことは姉の表情がどんどん頑なになり、歪み、髪が長くボサボサになっていく事からよくわかる。
親、特に、干渉の強い母への拒絶と憎しみがあるのだろうという様子が映像から伝わってくる。
姉が叫び、浴びせ続ける暴言は、母の喋り方そっくりとなってしまっている。
映画冒頭近くで相手の話をさえぎる母の怒涛の叱りつけを見た時には誰が病気の人かわからないくらいだった。
同じ喋り方、似ている声色、わーっと騒ぎ立てる人が二人いる感じだ。
姉は、自分が堪えて堪えて耐えきれなくなってきたものをそっくりそのまま母親に返している印象だ。
そして姉は症状のせいでアメリカに突然渡航してしまったことをきっかけとして、玄関ドアの内側には鎖と南京錠がいくつもつけられるようになった。
喋る声が小さかったり、高齢者独特の早口で状況説明が聞き取れなかったので、実際に鍵を設置したのは父か母かわからない。
両親は娘についてお互いに時々責任転嫁をする時もあるが、映画も進むと高齢化のためもあるだろう、諦念で娘の問題を直視は出来ない様子だ。
弟は姉の気持ちをほぐそうと時折語りかける。
弟から「(質問に答えてくれて)ありがとう」とお礼を言われると安らかな顔で頷く姉。
普段、親からは感謝をされたり、個人として認めたりしてもらえてない様子を感じる。
何をしていいかわからず10ヶ月も外出することのない母と娘。ただただ家族の加齢が進んでいく。
やがて、80歳を超えた母に認知症の症状が現れた事を皮切りに、医師から姉は精神病院に入院することと、母は父が在宅介護をするよう勧められてやっと事態は転換期に入る。
精神病院に三ヶ月入った姉に合う薬が見つかり退院。
帰宅した姉は朗らかな表情をみせ、身繕いを出来るようになり、応答もしっかりとし、ナスの味噌炒めという自炊までしてみせる。
合わない母とは衝突も無くなり、ストレスの無さが安定した生活を送れるようになっているように見える。
玄関ドアの内側からの施錠はようやく無くなった。
やがて母が亡くなり、姉はステージ4の肺がんが見つかって、姉に過ごしやすく過ごしてもらい、したい事をさせようという流れになる。
今度は父が脳梗塞になり、半身が麻痺した状態で車椅子生活を余儀なくされるようになった。
姉と父は二人で自宅に住み、なんとか生活は回っているようである。
ただ、朝食作り担当となった姉が作り出す朝食は夜中0時、時には出かけ先のコンビニで「自宅に包丁を持った男がいる」と助けを求めてしまい警察が訪問に来る事もあったので、統合失調症の寛解というものは難しいのだという事がわかる。
ふくよかだった姉がだんだん痩せ、癌の進行を感じさせる。
5年6年も経った頃だろうか、頭に帽子をかぶった姉、ベッドに横たわり心電計の波形が無くなる姉。
葬儀のシーンでは花に埋められ棺に横たわった姉の手元におそらく姉が好きであったであろうケーキが置かれ、その胸には研究論文?免状?ちょっと不明だが権威ある賞状のようなものが数枚重ねて父によって置かれる。
「姉の人生はある意味充実していた」と、最後まで病気を病気と見ず、勝手に結論づける父のセリフ。
一家は、母と姉という女性たちを喪って、男性たちだけが残される。
最後のシーンで弟は車椅子に乗り身体が傾いだ父に、姉が病気だとわかっていたのではないか?病院から連れ帰らず治療した方が良かったのではないかと、質問するというよりかは、詰問するような感じで問う。
しかしやはり、父は母のせいにする。
そして、これまで家族模様を撮っていたのは映画にするつもりだから、インタビューも載せるからということを了承してもらうシーン。
すんなり了承する父。
そこで映画は終わる。
感想
この一家とうちは、何だか似ていた。
そもそもこの映画を見るきっかけになったのは、とある掲示板でうちの辿った運命を書きこんだ時、レスをつけてくれた人がこの映画に家庭環境が似てますねと教えてくれたのだ。
まず、精神病の家族がいて家族の精神もすり減らしている状態が20年超のところが同じだ。
うちは決してインテリではなかったが両親と同じ世代だからか昔の価値観は似ていると思う。
「精神病というものは恥ずかしい、知られたくない、自分の遺伝から精神病が出るなんて考えたくない」
激しく感情を子にぶつける様子は、ここの一家でいう母がうちでは父な感じだ。
精神病本人はこの映画では姉だがうちは兄。
よく似ていることは、精神病である当人は状態が良い時で気を許した相手にはおどける。
黙って笑顔をつくりピースサインをしたり、片足を上げてひょうきんなポーズをとって写真に写るところが似ていた。
そして何より似ていたのは、当事者が肺がんになり早逝するしか、残された一家の運命が変わらなかった結末。
逆に違う点は、父よりも自分が病気だと認めたがらなかったのは精神病本人で、投薬されても薬をこっそり捨てていた。
映画の姉は躁状態で暴れるようだがうちの兄は喋らず、暗い表情で睨みつけるか、人の物を勝手に壊したり捨てるなどする八つ当たりをしていた。
映画の姉は監禁状態が長かったが、うちの兄は好きなこと(ライブ参加)をしに外出したり、作業所で少しお金を得ては喫茶店に通っていた。
また晩年近くには、少しは自省したらしき父が、自分が亡くなってからの兄の事を考えたらしく「家族の会」に参加したり奔走している痕跡が家じまいの時に発見された事だ。
違う点を並べ上げたところでどうでもいいか。
私が言いたかったのは、この似ている家族を見て、体験して、「どうすればよかったか?」私には言える。
一家の長、決定権を握るのは親。
この親に、精神病に対する理解や協力が無いと事態も病状も悪化をする。
初めが肝心なのだ。
良好な親子関係を結び信頼を持ち合うこと。
でも、良好な親子関係があれば、そもそも病気にはなっていないんじゃないか?、こういうプレッシャーのある家庭環境だからこそ病気の種が発芽したのではないか?という予感がある。
もしも、病気を認識することを拒絶し頑固な親だったら、この映画の家庭の場合は弟が無理やりにでも行動を起こして通院に結びつけられればよかったと思う。
無理やりというと語弊があるが姉と弟は好関係を結べている様子だったので、弟が気分転換と称して連れ出したり、通院させてしまえばよかった。
両親に感づかれたらごまかすか、できなければ男性なのだから、老いた両親より力や勢いで圧倒してでも強行すべきだった。
でも、この弟も、両親の前には屈している様子が感じられていたので無理か…
映画の冒頭のテキスト「これは誰が悪いということはない」
これは、家庭から逃げ出すことのできた監督が自分自身を庇う言葉でもあるように受け取っている。
「どうすればよかったか?」なんて、薄々わかってるんじゃないかな。
ただ、視聴者に何かを感じ取ってもらったり、考えてもらったりしてほしい映画じゃないかな。
自分と家族のすり減らした人生を無駄にしたくないという思いから。
私は、そんな思いもありこのサイトを作っているから、そうではないかなと勝手に同調して推測してみた。
蛇足、夫の感想
この映画を夫に説明した時、不快感を表した。
男性なんて力があるんだから如何様にも出来たろう、とか
何もせずに最初から撮り続けだけも親と同罪だしいつか飯の種にするつもりがあったから撮り続けたんだろう、とか
映画化を親に了承させたところを最後に入れる点が侵害を訴えられないよう予防線張っててズルい、とか
社会問題として提起するつもりなら今どきYouTubeで上げるのだって良かった、それを映画館のみにして1,800円の鑑賞料金とる?とか
そこまで強い言い方は私はしないけど、言いたいことは少しわかる。
それがなかったらすんなり観られていたかもしれないけど映画観てザワついた気持ちが残ったのはそういうことなんだろう。